ガイドラインの作成にあたって「公益信託の事業検討ワークショップ」が開催されています ~ 公益信託[69]
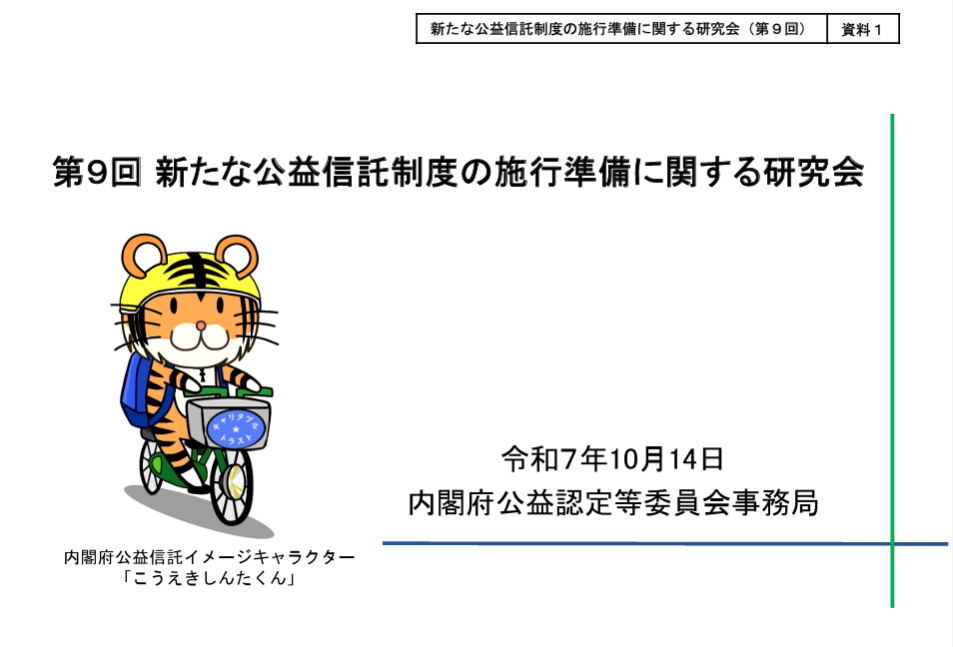
公益信託の記事を掲載します。
ワークショップを踏まえてガイドライン案に反映した内容とは?
を紹介します。
1 公益信託の引受事務に係る信託報酬について
Q:ワークショップにおける意見
「公益信託の設立手続き等に係る費用を信託報酬として得ることができるようにしてほしい?」
A:ガイドラインの対応方針
公益信託信託報酬については、引受時の公益信託事務(信託行為の作成、公益信託の認可申請当に係る専門家への相談)に係る信託報酬を受領することが可能な旨を明示しました。
2 公益信託事務の遂行能力について
Q:ワークショップにおける意見
「不動産を信託財産とする場合の留意事項とは?」
A:ガイドラインの対応方針
信託行為の内容、事業計画書および収支予算書の内容等を踏まえて、公益信託の存続期間において、公益信託事務が現実的かつ適切に処理される見込みであることについて、次のような観点から確認します。
① 金融的収入については、市場レベルを逸脱していないか?
② 寄附金収入については、実現可能なものと説明できるか?
③ 支出については、発生する項目や見積もり額が極端な過不足がなく、明らかに不合理なものとなっていないか?
たとえば、信託財産に「不動産」が含まれる場合、「不動産の所有に伴う支出(公租公課、管理費、修繕費等)を適切に算定されている必要がある。」を追加
④ 対価収入を予定する公益事務について、収益の見積もりの根拠(利用者数や単価など)が不合理なものになっていないか?
3 信託管理人の選任について
Q:ワークショップにおける意見
「地域や特定分野の中間支援組織が関与して信託管理人を選任することで、地域や特定分野の公益信託の活用に寄与できる?」
A:ガイドラインの対応方針
委託者が自然人である場合等で、公益信託の存続期間が長期に渡る場合には、次期信託管理人の選定手続としては
たとえば
① (前)信託管理人と委託者の協議によって(予め)定める者
② 弁護士、〇〇士や公益法人のうちから、合議制の機関の同意を得て定める者
③ 信頼できる第三者機関が推薦する者(追加分)
といった仕組みが考えられます。
(出所:第9回会議関係資料 内閣府公益法人行政担当室)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター・F.ドラッカー)
立冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
土・日・祝日は、ブログをお休みしております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


