「公益信託制度の施行準備に関する研究会」の公益信託認可ガイドライン案の「第4章公益信託認可の申請等」のうち「信託財産の運用について」について ~ 公益信託[46]
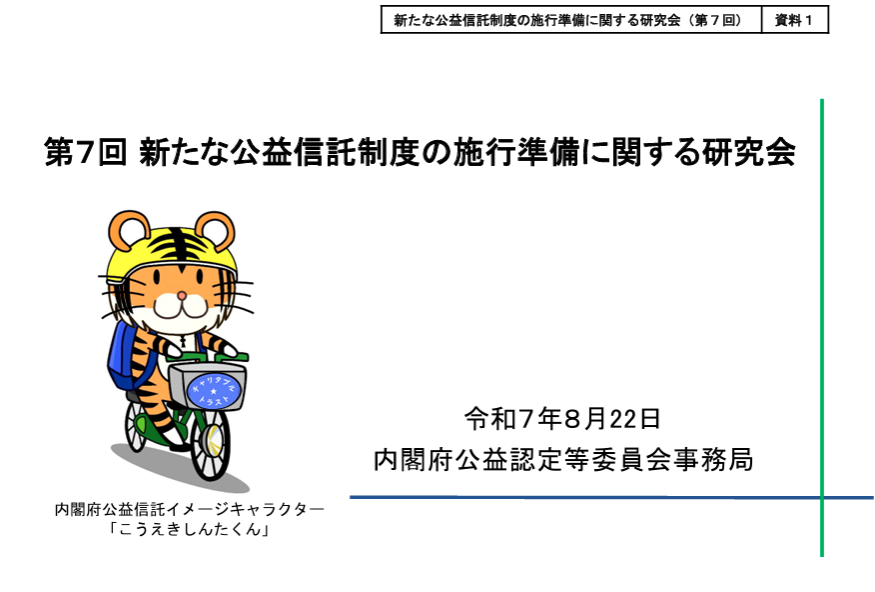
公益信託の記事を掲載します。
第7回の研究会(8/22)では「信託財産の受入れ、運用、支出その他の信託財産に関する事項」において「信託財産の運用について」について各委員から意見が出ています
を紹介します。
公益信託認可ガイドラインガイドラインは令和7年12月の策定予定です。
各委員からの意見は次のとおりです
① 金銭の運用について
信託行為に詳細が記載されていない場合は、受託者の能力も含めて厳しく審査すると理解した。公益信託における運用のイメージは、積極的にリスクを取るような運用ではなく、安定的な運用の方がデフォルトなのだろう。
② 信託財産に属する金銭の「運用」に係る信託行為への記載について
運用の専門家が受託者でない場合に運用してはいけないということまで言うつもりでない。説明資料P13 の②のところでポートフォリオ構成やリスク度合いまで信託行為に書くとしているが、これは資産運用に知見のない人が関与するときに安心であろうという理解。
信託銀行での実際の対応は、信託銀行では目標リターンなどまでは書いておらず、柔軟な運用ができるようにしている。委託者、受託者が意見交換をして柔軟な対応をしているが、ガイドラインはそういった専門家がならないケースを想定していることは理解。
ただし、期待リターンを信託行為で決める段階で、一義的に定められるかは疑問である。書く場合も書かない場合も出てくると思うが、ガイドラインに例示で記載するのはいいと思うが、これを必須にするというのは、書きすぎではないか。
③ 信託財産の運用について
期待リターンに適合できる分散運用を実施すること自体が運用の専門家でないと難しい。運用の視点を合意することを受託者に求めることは必要、期待リターンをどう作ろうとするのか理解していない人が運用しようとするのは大変でなので、運用の専門家と相談して対応してほしい。
④ 信託行為に運用方針を記載することは避けるべき
運用に関して、「利殖目的」とあるが、財テクのようなものであると適切でない。安全を求めすぎるのも適当でない。信託財産をきちんと分散投資をして収益をあげつつ、サステナブルに収益を公益に使っていくことを想定してガイドラインに記載されるべき。
今回は信託行為における記載として運用方針を決めることは、やりすぎではないかと感じる。財産の運用に関して専門家をきちんと使う、専門家に託すことも必要。運用はここ(ガイドライン)ではなく、行為基準にあたるようなところで専門家に頼むことを求めるようなことを書き、ここではそこまで求めないほうがいい。
行為の段階での専門家の活用にシフトすべきで、最初の時点から信託行為に運用方針を記載することは避けるべき。
(出所:第7回会議関係資料 内閣府公益法人行政担当室)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
金曜日は公益信託の記事を掲載しております。
土・日・祝日は、ブログをお休みしております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


